

明治10年(1877)に黒川が開削された。明治維新からわずか10年後、九州では日本最後の内戦である西南戦争が起こっていた時代である。なぜ、この時に黒川を造る必要があったのだろうか。
明治になり時代が大きく変わり、名古屋は城下町から工業都市へ変わる必要があった。また、当時最大の産業である農業を振興する必要もあった。このため、舟運路を充実させ、より多くの農業用水を確保する壮大な構想がたてられ、その一部として黒川が開削されたのである。
 |
|||
 |
|||
明治10年(1877)に黒川が開削された。明治維新からわずか10年後、九州では日本最後の内戦である西南戦争が起こっていた時代である。なぜ、この時に黒川を造る必要があったのだろうか。 明治になり時代が大きく変わり、名古屋は城下町から工業都市へ変わる必要があった。また、当時最大の産業である農業を振興する必要もあった。このため、舟運路を充実させ、より多くの農業用水を確保する壮大な構想がたてられ、その一部として黒川が開削されたのである。 |
|||
| |
|
|
|
名古屋活性化の壮大な構想 |
|||
| ◇輸送力が貧弱な名古屋 明治になり名古屋が城下町から産業都市に変身するには、輸送力の不足という大きな問題があった。近代産業は工場での大量生産だが、そのためにはたくさんの原料や製品を早く安く輸送できないと他の産地との競争に負けてしまう。当時、大量に輸送できるのは舟しかなかった。名古屋の舟運路は堀川しかなく、堀川は南の熱田にしか繋がっていない。名古屋と北方の尾北や美濃などとの舟運は、木曽川経由であった。木曽川を下り桑名へ出て、伊勢湾を横断して熱田へ、さらに堀川を遡上して名古屋という大変な迂回であった。 |
|||
| 堀川の輸送は熱田で海運と連結していたが熱田湊は水深が浅い港であった。このため少し大きな船は入港できず、西洋型船が造られて船が大型化すると天然の良港であった四日市港や武豊港が利用されるようになっていった。熱田湊は干潮になるとごく小さな舟以外接岸ができないという貧弱な湊であった。 ◇農業用水が不足する名古屋周辺の農地 当時は日本の一番大きな産業は農業であった。名古屋も現在の北・西・中村・中川・熱田・港区には広大な農地が広がっていて、潅漑には庄内用水が使われていた。しかし、水源の庄内川は流量が少なく水不足に悩んでいた。 ◇名古屋の起死回生……壮大な計画 これを解決するために明治9年(1876)から17年(1884)にかけて次の事業が行われ、19年(1886)から犬山と名古屋を結ぶ舟が行き来するようになった。 ・新木津用水の拡幅 ‥‥流量を増やし、併せて舟が通れるようにする。 ・庄内川と堀川をつなぐ新しい水路(黒川)を造る‥‥舟の通行 ・庄内用水路の付け替え‥‥用水の流量増加による農業振興 ・熱田港の浚渫と波止場の築造‥‥他の地域との海運を活性化 |
犬山と名古屋を結ぶ航路 『尾張国全図』 明治12年 |
||
|
黒川開削工事 |
|||
|---|---|---|---|
| 構想の中で最初に行ったのが黒川の開削である。明治9年(1876)11月に「庄内川分水工事」として事業が始まった。 今の水分橋(現:守山区)のたもとに元杁(もといり)樋門を設けて南に向けて水路を掘り、三階橋の北で現在の守山区内の排水を集めて流れてくる八ヶ村悪水を合流。矢田川は伏越(ふせこし)で川底をくぐり南岸の辻村(現:北区)へ出る。ここで堀川へ流れてゆく新しい水路(黒川)と御用水や庄内用水などを分流させる。堀川へは、御用水に沿って南西に向かう新しい水路を掘り、今の猿投橋のところで従来から堀川に流れ込んでいた大幸川に接続。それより下流は大幸川を改修した。 工事は10年(1877)10月に完成し、総工費は3万9千円であった。 新しくできたこの川は、工事を担当した愛知県技師 黒川治愿の名から「黒川」と名付けられた。現在の河川法では、水分橋際の元杁樋門(取水口)から名古屋港までの全川が「堀川」になっているが、今も朝日橋より上流は「黒川」と呼ばれることが多い。 |
下図は明治22年地形図 |
||
|
黒川開削による水系の変化 |
|||
|---|---|---|---|
| 黒川開削事業の中で関連する河川や水路の付け替えが行われ名古屋北部の水系は大きく姿を変えた。 ◇御用水 黒川開削以前は龍泉寺の麓で庄内川から取水して名古屋城まで水を送っていた。黒川の開削により、守山区内の旧御用水路は取水位置を少し変えて八ヶ村用水となり、余り水は古川を経由して黒川に流入するようになった。 姿を変えた新御用水は、矢田川伏越の出口で黒川から分流してお城へ流れるようになった。 ◇旧八ヶ村悪水(古川) 黒川開削以前は三階橋北で御用水を伏せ越し、すぐ下流で旧庄内用水へ流入していたが、黒川の開削により黒川へ流入する川になった。名称はその後古川と呼ばれるようになっている。なお、現在は守西ポンプ所で矢田川に排水している。 ◇庄内用水 黒川開削以前は三階橋の北で御用水から分流し、川中三郷(成願寺・中切・福徳村)を流下して、福徳村で矢田川を伏せ越して稲生村へ出て西へと流れる川であった。 黒川の開削により、矢田川伏越の出口で黒川から分流し、新たに当時の矢田川堤防に沿って開削された水路で西へ流れ、稲生村で旧水路へ流入するように変わった。 ◇大幸川 黒川開削以前は大幸村(現:東区大幸町など)付近から流れ出し、御深井の庭の北と西を流下して朝日橋で堀川ヘ流入していた。 黒川の開削により、現在の猿投橋より下流は黒川になり、それより上流の大幸川は黒川の支流となった。 |
|||
|
|
|
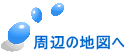  |
|