
明和4年(1767)、この地方を豪雨が襲った。矢田川はそれまで長母寺の南を流れていたが、激流は北側の守山丘陵鞍部を乗り越えてまっすぐに流れるようになった。また左岸が破堤して濁流が城北地域を西へと流れ、城西地域は水深1.4mになった。領内各地で大きな災害が起き、犠牲者は2,000人余と記録されている。
この大災害を契機に、白沢川や大幸川の瀬替や新川の開削なども行われた。
 |
||
明和4年(1767)、この地方を豪雨が襲った。矢田川はそれまで長母寺の南を流れていたが、激流は北側の守山丘陵鞍部を乗り越えてまっすぐに流れるようになった。また左岸が破堤して濁流が城北地域を西へと流れ、城西地域は水深1.4mになった。領内各地で大きな災害が起き、犠牲者は2,000人余と記録されている。 この大災害を契機に、白沢川や大幸川の瀬替や新川の開削なども行われた。 |
||
| |
|
|
洪水をきっかけに 他の川も大改修 |
|||
|---|---|---|---|
| 財源不足に悩む尾張藩であったが、明和4年(1767)の大洪水とその後も起きた洪水により、各地で大規模な治水工事を行っている。 ◇白沢川 白沢川は守山丘陵の水を集めて西へ流れる川であった。いったん大雨が降ると下流部の守山村・幸心村・瀬古村・山田村(矢田川北の飛び地)で溢れる暴れ川だったが、明和4年(1767)の大雨でも下流部に大きな被害を与えた。 このため、瀬古村などの願いにより、翌5年(1768)に川村で川を横断する堤防を造り、新しい水路を掘り近くの庄内川に流入するよう改造された。これにより上流部の水は庄内川へ流れ、築堤より下流地域の水だけが瀬古村へ流れるようになった。新しく掘った水路が白沢川と呼ばれ、旧河川は古川(山下悪水・八ヶ村悪水・五ヶ村悪水)に名が変わり現在の姿になったのである。 ◇大幸川 城北地域を西へ流れた洪水がなかなか引かなかったのは、地域の幹線排水路である大幸川が笈瀬川に流れ込んでいたためである。流入先の笈瀬川は勾配の少ない低平地を流れる狭くて浅い川で、十分な流下能力が無かった。このため水が溢れ易く、一度溢れるとなかなか水が引かないという問題を抱えており、被害を拡大していたのだ。 大幸川の排水能力を高め、併せて笈瀬川の負担を軽減するために、大幸川上流部の流域を切り離して、河川断面が大きく直線的に流れていて排水能力が高い堀川の流域に変更する工事が始まった。 東志賀村(現:北区志賀町)の御用水と交差する所から御用水にほぼ並行して新たに水路を掘り、名古屋城の御深井の庭の中を掘り割って堀川へと流れ込む延長1里(4㎞)ほどの新しい大幸川が造られた。工事が始まったのは天明4年(1784)11月、翌年3月になると、当初は「辰之口橋」と名付けられた朝日橋が、4月11日には大幸橋が完成している。 工事が明和4年(1767)の洪水から17年後になったのは、この頃藩はすでに経済的に余裕がなく、大規模な土木工事ができなかったからである。 明和4年(1767)の洪水後も何度も水害が発生した。安永8年(1779)8月の大雨で庄内川が増水し、庄内・矢田川以南の城北地域は大きな被害がなかったものの、志段味・味鋺・大野木など各所で破堤し大水害が起きた。このため9代藩主宗睦は、勘定奉行であった水野千之右衛門と参政の人見弥右衛門に治水計画の検討を命じた。その後も天明2年(1782)には五条川や合瀬川が破堤、翌3年(1783)には庄内川が大野木で破堤するなどしている。このような状況の中で大幸川の流路変更は、新川の開削などと共に行われたのである。なお、この頃は天明の大飢饉のさなかで、副次的には窮民救済の効果もあったと考えられる。 ◇新川開削 味鋺と大野木の村境に庄内川の堤防を一段と低くした洗堰を設けて、庄内川の水が5合(計画高水位の半分の高さ)に達したら大蒲沼に流れ込むようにし、庄内川右岸に平行して海まで延長20㎞に及ぶ新たな川を掘り排水する。あわせて、これまで庄内川に流れ込んでいた大山川、合瀬川(木津用水)、五条川などを新川につなぎ庄内川の負荷を減らすという壮大な構想で行われた。 この大事業は、当時の尾張藩の御蔵米ぜんぶを売り払っても足りない約40万両というばく大な費用が必要であり、ふつうの手段ではとうてい藩の許可は得られない。御普請奉行の水野千之右衛門は自分が犠牲になってでもこの大事業をやり遂げる覚悟で、きわめて低額な見積もりを藩に提出し工事を開始した。さらに、工費不足になり工事半ばでの中止がされにくいように、工区を200にも分けて御冥加人夫(村々から義務として出る人夫)を増やし、大幸川の流路変更と同じ天明4年(1784)に、全工区をほとんど同時に着工した。 はたして、工事が3分の1も進まないうちに事業費の不足が判明し、藩内では水野に対する批判の声が高まってきた。藩は幕府からの借金や豪商からの調達金でしのいだが、万策きわまり工事は中断、天明6年(1786)10月1日に水野千之右衛門は免職となり閉門蟄居を命ぜられた。しかし、全区間で中途半端に工事が行われてしまっている。完成を心待ちにしている農民たちの声に押されて、藩は再び水野を御普請奉行に任命し工事が再開された。水野の周到な計略どおりはこんだのである。 着工から3年の歳月を経て、天明7年(1787)に新川が完成した。 |
|||
|
|
|
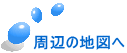  |
|