

江戸時代初期、畑から石仏が出てきた。お堂に祀ると人々が参拝し、御利益が大きく人気が高まった。お婆さんが掘り出した薬師様なので「祖母の薬師」と呼ばれていた。江戸時代末期に瑞忍寺へ改称している。
 |
|||
 |
|||
江戸時代初期、畑から石仏が出てきた。お堂に祀ると人々が参拝し、御利益が大きく人気が高まった。お婆さんが掘り出した薬師様なので「祖母の薬師」と呼ばれていた。江戸時代末期に瑞忍寺へ改称している。 |
|||
|
|
|||
| 百事山瑞忍寺は真宗大谷派の寺である。 ◇畑から石仏 瑞忍寺創建の由来について『尾張名陽図会』は次のように記している。 「元和年中(1615~23)、当所に源左衛門といふ百姓の後家が、居みし屋敷の畠にて石仏を掘り出しけるが、古くなりて面体も分らず。小仏なれば大黒と思ひ安置す。ある夜その後家が息女に託して、我は薬師なりと告げさせ給ふ。それより堂を建立しすなはち本尊とす。ある年戸を開きて諸人に拝しむ。次第に霊験あらたにして祈願の人多くなれり。寺院の号も無きものから、かの後家老年に及びし事なれば、祖母(ばば)が薬師と云ひならせしなり。しかるに年月を経て、延宝7年(1679)、本寂といへる僧ありて堂守となり。堂宇を再興せしとかや。」 |
|||
江戸時代初期にお婆さんが畑から石仏を掘りだし、それが薬師仏と知ってお堂を建立し祀った。参拝する人が増えたものの名前がないので、お婆さんが掘り出しとことから「祖母(ばば)が薬師」と呼ばれた。延宝7年(1679)に本寂房常照が堂守になり再興したとのことだ。 |
 「尾張名陽図会」 |
||
| 『寺社名録』には、石仏は長さ1寸(3㎝)余で弘法大師の作と書かれている。 ◇祖母薬師から瑞忍寺へ 永らく祖母(ばば)薬師と呼ばれてきたが、文久3年(1863)に、瑞忍寺と名を改めた。なお、本尊は阿弥陀如来立像である。 ここから400mほど下街道を北へ行くと阿弥陀院円満寺がある。ここの薬師は元は田中薬師と呼ばれたのを明暦(1655~8)頃に寺内へ遷座したもので行基作と伝えられ、祖母(ばば)薬師に対比して祖父(じじ)薬師と呼ばれていた。 |
|||
|
|
|
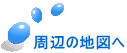  |
|