
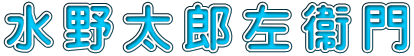
東片端交差点の東に「鍋屋」という調理器具の専門店がある。ここのご先祖は、藩の鋳物師頭を務めていた。藩内の鍋や釜などの鋳物品取扱の元締めであり、大砲など兵器の製造も行う重要な役割を担っていた。
 |
|||
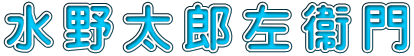 |
|||
東片端交差点の東に「鍋屋」という調理器具の専門店がある。ここのご先祖は、藩の鋳物師頭を務めていた。藩内の鍋や釜などの鋳物品取扱の元締めであり、大砲など兵器の製造も行う重要な役割を担っていた。 |
|||
|
|
||
| 東片端南交差点を通る東西道路が下街道で、交差点から東の旧町名は鍋屋町である。交差点東南角には「鍋屋」という名前の、鍋を主体にした調理器具専門店がある。 このあたりは江戸時代、鍋や釜などの鋳物が盛んな地域だったので鍋屋町と呼ばれ、この地域の町代役を勤めていたのが「鍋屋」の先祖の水野太郎左衞門だ。 ◇鋳物師頭 水野氏 水野氏は、元は春日井郡鍋屋上野村で鋳物業をしていた。元亀2年(1571)に信長から領内での鋳物製造の独占権を得、文禄2年(1593)に清須へ移住した。その後、慶長16年(1611)の清須越しで清須の鍋屋町が町ぐるみこの地へ移転した。 鋳物師(いもじ)頭の水野氏は、徳川氏からも従来通り鋳物業の独占権を認められた。藩から3人扶持を支給され、長さが18間(32.8m)、幅が10間(18.2m)ある鋳物工場兼屋敷は、諸役免除・御目見得が許される家柄であった。また、藩内では水野氏の許可を得ず、鐘・鰐口・鍋・釜などを売買することは禁止されていた。 ◇大砲も鋳造 このように藩から厚遇されたのは、当時の大砲は鋳物で造ったからである。 幕末に、藩は軍事力を強化するため水野氏に大砲鋳造を命じている。 『松濤掉筆』の嘉永6年(1853)9月14日の記載に「桑名から熱田に金銅25駄分が到着した。今回大坂で150駄分買い上げた内の一部だ。すぐに馬で鍋屋町の鋳物師頭のところへ運ばれた。皆、新しい大砲を作る材料である」という内容の記録が残っている。 この年の6月3日に浦賀に黒船が来航した。海岸の防備を固めるため武器の増産が必要になり鋳物師頭の水野氏に大砲の製造が命じられ、3か月後の9月にその材料が届いたのである。 この大砲と考えられる関連記事が、『感興漫筆』の嘉永6年のところに記録されている。 「今度、新たに鋳造された鉄砲(大砲)の銘を選ぶよう、御用人から明倫堂(藩校)督学に命じられた。」という趣旨のことが書かれ、続いて銘を付ける大砲の種類と砲数が記録されている。 長さ1丈3尺(3.9m)、砲弾5貫(18.8㎏)の迦農〔加農(カノン、キャノン)砲 〕を始めとして、カノン砲が3種類で16門ある。ほかに三忽礟(不明、礟はホウと読み石弓の意)が5貫(18.8㎏)と3貫(11.3㎏)の砲弾を使用するもの合わせて16門となっている。 なお、江戸時代後期の太郎左衞門は暦に関心を持っていたようで、伊能忠敬が下街道の測量をして名古屋の宿舎にいるところへ聞きに行った記録が残っている。『尾三測量日記』、文化8年(1811)3月22日のところに「鍋屋町水野太郎左衛門と云用達町人暦術を聞ニ出ル」と書かれている。 |
||
|
|
|
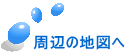  |
|