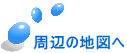|
元治元年(1864)11月、尊王攘夷の旗の下に決起した水戸天狗党の志士たちが、大砲をたずさえ大挙して中山道を京都にむかっているとの報が名古屋に届いた。下街道の入り口、大曽根は戦争の準備でたいへんな騒ぎになった。
◇水戸天狗党とは?
幕末の動乱期、水戸藩も尊皇派と左幕派に藩論が二分していた。
尊皇攘夷をとなえる天狗党は、藩内での抗争に破れ、ついに元治元年3月筑波山(現:茨城県)で挙兵し、京都にいた水戸藩主 一橋慶喜(よしのぶ、後の15代将軍)に会い、直接自分たちの考えを訴えようとした。
元家老の武田耕雲斎を総大将にして1,000名もの志士達が200頭の騎馬と15門の大砲を携え、11月1日に常陸大子〔現:茨城県大子(だいご)町〕をたち、「奉勅」「大和魂」「報国」などと書かれた幟をなびかせつつ中山道を京都にむかった。
◇幕府から追討令
沿道の各藩は幕府から追討の命令を受けており、天狗党の上京を阻止するべく戦闘が始まった。
11月16日には追撃してきた高崎藩兵と下仁田(現:群馬県下仁田町)で激しい戦いになり、天狗党は4名の戦死者を出したものの、高崎藩兵36名を討ち取った。さらに西に進み、20日には和田峠(現:長野県長和町)で待ち受ける松本藩・高島藩と交戦し敗走させた。
その後、天狗党は伊那街道(伊那谷)を飯田にむかい、清内路峠(現:長野県阿智村)を越えて26日には木曽の馬籠(現:中津川市)まで進んできた。沿道の藩は、高崎藩や松本藩などの敗北を知っていたので、抵抗することなく一行を通過させた。
◇尾張藩 大曽根などに守備隊を配置
こうした情勢に、名古屋城下でも天狗党が伊那街道を南下している20日過ぎからうわさが広がりはじめた。
尾張藩は、御三家筆頭で全国でも有数の大藩である。天狗党が城下を通行するのを黙認したり、戦って敗れることがあっては、面目は丸つぶれとなる。27日から城下の出入口である、大曽根・出来町・清水・末森など9か所に守備隊を配置し警備を固めた。
下街道が通る大曽根口では、善行寺(現:東区徳川二丁目)に本陣(戦争の指揮をとる所)をおき、野呂瀬半兵衛が隊長で防備を固めた。付近の寺はもちろん、広い民家も宿舎にあてられた。しかし、集まった藩士は、鎧・兜に身を固めた者、籠手(こて)や脛当(すねあて)など小具足姿の者、陣羽織や火事羽織の者など、太平の世に慣れた武士があわただしく参集したことが感じられる光景であった。
『感興漫筆』などの著者として知られる細野要斎家にも、27日の朝に即刻出来町へ来るよう命令が伝えられた。息子の得一が午後1時頃に出立したが、具足は持っておらず、12月2日に藩から貸具足を受け取っている。
大曽根周辺の住民たちは、女性や子どもを避難させたり貴重な家財を運び出したり、たいへんな騒ぎになった。
この間、天狗党は中山道を南下し、28日には大井宿(現:恵那市)で宿泊。翌29日はとうとう槙ケ根の追分にきた。
右に進めば中山道、左に進めば大曽根に続く下街道である。藩が派遣した遠見の者(偵察)も、息をのんで見つめている。天狗党はそのまま中山道を進み、この日は御嵩(みたけ)宿(現:御嵩町)で宿泊した。翌30日は名古屋に続く稲置街道(木曽街道)が分岐している伏見宿(現:御嵩町)に達したが、ここも中山道を西にむかい、名古屋を迂回して進んでいった。
尾張藩の厳戒態勢は12月11日に解除されている。
◇その後の天狗党
12月1日には揖斐(現:岐阜県揖斐郡)に到着した。その後、根尾村(現:本巣市)から蝿帽子峠(現:廃道)を越え12月4日には越前の大野(現:福井県大野市)へ入った。
その後、木の芽峠(現:福井県南越前町)を越え新保(現:敦賀市)に到着したが、そこには1万を超える大軍が布陣し、指揮していたのは天狗党が希望のともしびとしてきた慶喜であった。
ついに万策尽きた天狗党は、12月17日、近くで対峙していた加賀藩に降伏を申し出た。翌元治2年(1865)2月には、投降した800余名のうち353名が斬首刑となった。
|