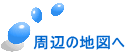|
日本初の鉄道営業路線が、明治5年(1872)9月開通の「新橋~横浜間」であることはよく知られている。では愛知県で初めて開業した路線は?。
じつは知多半島の武豊港と名古屋を結ぶ武豊線だ。武豊線は東京~神戸間の大動脈建設に向け、はじめは中山道経由の鉄道を造るために計画され、明治19年(1886)3月に開業した資材運搬線であった。鉄道建設資材を海上輸送し陸揚げする基地となった武豊港(熱田港は水深が不可)のある武豊駅から熱田駅間がまず開業し、4月には笹島の名古屋駅まで延伸した。同年7月、中山道経由の路線が技術経済面から困難と判断されて東海道経由に変更されるにいたる。その結果、東海道線建設のために活躍することとなった武豊線は、東海道線の開通〔全通は明治22年(1889)〕にともない、大府駅~名古屋駅間が東海道線の一部となった。
当時、初めて堀川に架かった鉄橋は替えられたものの、その橋脚は140年たった今も現役で堀川を渡る電車を支えている。まさにほりかわでの最古参の土木遺産だ。
◇愛知はレンガの生産地
愛知県はレンガの生産地として全国有数で、ノリタケ・カンパニー工場(岡田煉瓦製造所)、名古屋市政資料館の前身・旧名古屋控訴院(名古屋監獄工場)など、幾多の大地震をくぐり抜けてきた建造物も多い。鉄道トンネルでは愛岐トンネルの調査から数多くの煉瓦工場が特定されている。堀川の橋脚はとりわけ時期が早く、1886年以前に実績のある工場としては、士族授産所として1882年に設立された東洋組刈谷支部・西尾支部とその派生工場が煉瓦製造の候補にあげられる。
こうした観点から、堀川にかかる煉瓦積みの古い橋台(五條橋など)を調査してみるのも、興味深そうだ。
(川角信夫氏記述)
|