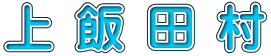
矢田川の南に位置する上飯田村は、水害に泣かされてきた村であった。村絵図を見ると、決壊して砂入になってしまった耕地がある。古記録には年々矢田川の川底が高くなるにつれ田の湧き水が増え、低温障害で稲が実らなくなったことが書かれ、村の人口は6割に減少してしまっている。
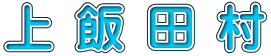 |
||
矢田川の南に位置する上飯田村は、水害に泣かされてきた村であった。村絵図を見ると、決壊して砂入になってしまった耕地がある。古記録には年々矢田川の川底が高くなるにつれ田の湧き水が増え、低温障害で稲が実らなくなったことが書かれ、村の人口は6割に減少してしまっている。 |
||
| |
|
|
|
| |
|
|
|
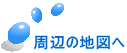  |
|