
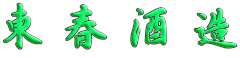
 |
|||
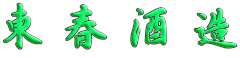 |
|||
| 下街道沿いに東春酒造がある。江戸末期の創業で時代の波に翻弄されながらも今も続く老舗酒蔵だ。伝統的な山廃仕込みで作られた酒は、スーパーに並んでいる量産品とは一線を画した味である。 |
|||
|
|
|||
| 東春酒造は、元治2年(1865)に創業した造り酒屋で、今も山廃仕込みという昔からの醸造法で酒造りを行っている。 ◇下街道沿い 守山きっての繁華街 この辺りは今は静かな住宅街だが、江戸時代から明治初期にかけては現在の守山区内で一番賑やかな土地だった。 『守山区の歴史』によると、江戸時代の守山村には商人5人が居たが瀬戸街道沿いに商店はなく、明治11年(1878)になって酒造業や米穀業、菓子小売業などが現れた。この時点で下街道沿いの瀬古村では、旅籠2軒、小料理屋2軒を始め24軒の商店が有ったという。 旅籠に泊まる旅人や、小料理屋に入った龍泉寺参りや矢田川や庄内川に行楽に来た名古屋城下の人、近在の農民達が、ここの酒を飲み一時の楽しみとしたことであろう。 ◇江戸末期に創業→戦時中に廃業→戦後に再興 『守山市史』に東春酒造について次のように書かれている。 「瀬古村には江戸末期、桝屋弥左エ門が小規模な酒造業を営んでいたが、永続せずして廃業した。つゞいて佐藤藤兵衛(東春酒造ホームページでは東兵衛)が酒造業を創め「龍田屋」と号し庄内川の水を運んで醸造用水に使用し、相当手広く経営していた。生産された酒は「菅公」の商標で売出し、永く世人に知られていた。佐藤家はその後代々この業をついだが、昭和18年(1943)戦時企業整備によって廃業した。戦後、以前の同業者有志を株主とする東春醸造株式会社を創立して、現在も醸造をつゞけている。」 なお同社のホームページによると、「菅公」ブランドは高牟神社に菅原道真の絵があったことにちなんで付けられた。しかし、他社が商標登録をしたので使えなくなり、当主の名の東兵衛から「東」、屋号の龍田屋から「龍」をとり、大正10年(1921)から「東龍」に変えたとのことである。 酒造りには良い水が必要だ。ここは天井川の庄内川と矢田川に囲まれた輪中地帯で、『尾張徇行記』には「卑湿の地ナリ」と書かれている様に地下水位が高く水には不自由しない場所である。街道沿いの賑やかな場所という立地もあって東春酒造は繁盛し、今もおいしい酒を造っている。 |
|||
|
|
|
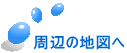  |
|