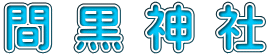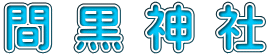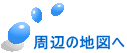|
間黒(まぐろ)神社の創建は、『東春日井郡誌』に「社伝明らかならず」と書かれ不明であるが、旧社格は村社である。
創建の時期は不明であるが、『尾張徇行記』に「前々除」とあるので、慶長13年(1608)の備前検地以前から存在しており非課税地扱いだったことが分かる。
祭神は、須佐之男(すさのお)命・大山祇(おおやまづみ)神・市杵島比売(いちきしまひめ)命・多紀理比売(たきりひめ)命・多紀津比売(たぎつひめ)命・天照大御神の6柱だ。数が多いように思われるが、大山祇神以下の5柱は他から遷座してきた神様である。
『尾張徇行記』の幸心村の記述には「社五ケ所 天王・神明・白山・山神・弁才天 界内三反四畝前々除」とあり、間黒神社の名前は出てこない。村絵図を見ると間黒神社の所には氏神社と書かれ、南隣に神明社があり、山神社・弁天社・白山社は村内に散在している。
『徇行記』に書かれている天王社(牛頭天王=須佐之男命)が氏神社で、現在の間黒神社の元だ。
明治11年(1878)に村の北の方にあった白山神社〔菊理比売(くくりひめ)命=白山比咩(しらやまひめ)神〕がここへ遷座してきた。
44年(1911)に山神社(大山祇神)と市杵島社を合祀した。市杵島社は『徇行記』に書かれている弁財天社である。明治になり神仏分離が行われ、弁財天は宗像(むなかた)三女神とされた。市杵島比売命・多紀理比売命・多紀津比売命の3柱もこの神社に祀られることになったのである。
さらに大正2年(1913)に神明社を合祀し(祠は前の場所のまま)、天照大御神も祭神に加わった。間黒神社は境内を古川が横切り、橋を渡って拝殿に向かう。橋の名は、間黒橋と思いきや神明橋である。橋の南はかつての神明社境内だったからである。
本殿左に御嶽神社と津島神社、右手に秋葉神社・金比羅神社・奥山半僧坊・白山神社、少し離れて山神社が鎮座している。
|