
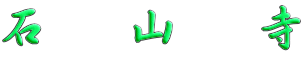
 |
|||
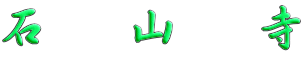 |
|||
| 矢田川の北、かつての下街道(善光寺街道)近くにあるのが石山寺である。鎌倉時代に創建され、戦国時代には衰退したものの尾張藩主が再建し、広く落ち着いた境内は歩んできた永い歴史を今に伝えている。 |
|||
| |
|
|
|
| |
|
石山寺への道標 |
|||
|---|---|---|---|
| 寺の北東、駐車場の一隅に石柱が建っている。風雪に削られて読みづらいが、「右 石山寺道」「寛政七卯五月吉日」と彫られている。 1795年に下街道際に建立され、右へ行くと石山寺と案内しているので、下街道を北から名古屋方面に来た人を対象に案内した道標である。村絵図を見ると、八ヶ村悪水(現:古川)南岸に天王社があり、そこから石山寺への道が延びているので、そこに建てられていたと考えられる。 |
 |
||
|
|
|
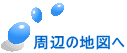  |
|