

常光院は、江戸時代初期に矢田川北の地から移転したとも、念仏堂から発展したとも伝えられる寺である。
境内には寛文3年(1673)と刻まれた一対の鬼瓦や名古屋築城時の落し石が保管され、寺と地域の歴史を伝えている。
 |
|||
 |
|||
常光院は、江戸時代初期に矢田川北の地から移転したとも、念仏堂から発展したとも伝えられる寺である。 境内には寛文3年(1673)と刻まれた一対の鬼瓦や名古屋築城時の落し石が保管され、寺と地域の歴史を伝えている。 |
|||
|
|
|||
| 降華山常光院は真言宗智山派の寺である。 『尾張徇行記』によると元は等覚寺といい、旧矢田川の北にある大寺であったが、何度もの水害で寛永年間(1624〜44)に現在地へ移転したという。なお今の常光院へ名前が変わった時期は不明としている。 また、元和年間(1615~24)に宥賢和尚が、長久寺(現:東区)の念仏堂として結んだ寺ともいう。たび重なる洪水に苦しむ村人たちの信仰によって支えられてきた寺である。 境内には、そんな地域とのつながりを示す遺物が残っている。 「寛文十三年みつとのうし七月吉日 いせ山田西せこ高井六兵衛作」と書かれた1673年作の阿吽一対の鬼瓦がある。 これは、近くの「大久」から寄贈されたものだ。大久とは菅原道真の画像を所有していた質屋大坂屋である。初代の大坂屋は、石田三成の家臣であったが、関ケ原の乱をのがれて、山田の庄にきたという。大久は、屋号の大坂屋と名前の久兵衛をとって呼ばれたものである。大坂屋久兵衛から暖簾分けをして、酒屋を始めたのが、国道十九号に面して立つ金虎酒造である。 また、境内には築城時の落とし石が置かれている。 |
|||
 一対の鬼瓦 |
鬼瓦側面の製作者等の記入 |
 落し石 |
|
|
|
|
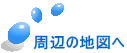  |
|