
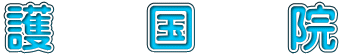
立派な山門がそびえる護国院は、はるか昔 天平時代に行基が創建したと伝えられている古刹である。きれいに整えられた境内には、地域の歴史を伝えるさまざまなものが残されている。
 |
|||
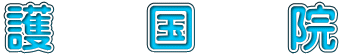 |
|||
立派な山門がそびえる護国院は、はるか昔 天平時代に行基が創建したと伝えられている古刹である。きれいに整えられた境内には、地域の歴史を伝えるさまざまなものが残されている。 |
|||
| |
|
|
魅力あふれる境内 |
|||
|---|---|---|---|
| ◇山 門 山門は2階建になっており、2階には高欄が巡らされた立派なものだ。 珍しいのは門を守っている像。普通は仁王が立っているが、ここでは四天王が山門の表に2体、裏に2体立って目を光らせている。他の寺ではほとんど見かけないものである。 |
|||
山門の表側 |
山門の裏側 |
||
| ◇不動堂 本堂の右手には木造の不動堂がある。これは以前の本堂だ。中には脇侍の不動明王が祀られている。 正面の格天井に絵がたくさん嵌められている。今では古びているが、かつては極彩色の華やかなものであったろう。これも他では見ることができないものである。 |
|||
 |
 |
 |
|
| ◇古墳の石棺 参道左の祠に、岩屋堂古墳(現:廃滅)から出土した石棺が納められている。 岩屋堂古墳は早い時期に滅失したようだがこの寺との縁は深く、江戸時代末期に編纂された『尾張名所図会』には護国院に付属する岩屋堂があり、十一面観音が本尊で尾張三十三観音の一つと書かれている。 また、1800年前後に編纂された『尾張徇行記』には「護国院が所蔵している古鏡と古剣は元文4年(1739)に岩窟堂(岩屋堂)の跡地から発掘されたもの」と書かれている。また、岩屋堂にあった正観音像は編纂された頃には護国院へ移転していたとのことである。 |
|||
 |
 |
 『味鋺村絵図』 |
|
| ◇道標の石仏 山門近くに、無縁仏が幾体も祀られた山がある。そのなかには、元禄の年号の入った古仏もある。 山の下にある頬に手をあてた観音像は上部が壊れセメントで補修されているが「川道」の文字が残り、「勝川道」の案内をする道標であった。 また別に「右勝川莊 左小牧莊」と彫られた石仏もある。 |
||
 勝川を案内する石仏 |
 右勝川莊 左小牧莊を 案内する石仏 |
|
|
|
|
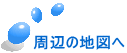  |
|