
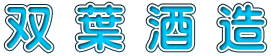
稲置街道沿いに残る旧家の建物、窓ガラスに「曲水園」と書かれている。かつては造り酒屋だった家だ。街道を行き来する人々と紡いだ歴史が深くしみこんでいる建物である。
 |
|||
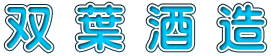 |
|||
稲置街道沿いに残る旧家の建物、窓ガラスに「曲水園」と書かれている。かつては造り酒屋だった家だ。街道を行き来する人々と紡いだ歴史が深くしみこんでいる建物である。 |
|||
|
|
|||
| 稲置街道を護国寺に向けて歩いてゆく。往時の名古屋と犬山とをつなぎ何人もの旅人が往来した街道も、現在では、自動車がすれ違うのも難儀な狭い道になっている。 | |||
| 新地蔵川を渡り、首切地蔵を過ぎると通りの左手に、木製の「忍び返し」のついた塀が続く旧家がみえる。 「忍び返し」は、盗賊などが忍び入るのを防ぐために、塀の上に木や鉄をつらね立てて取りつけたものだ。屋敷に忍び入ろうとした盗賊が、塀に上ったものの鋭くとがった木や鉄が取りつけてあって内部に入ることができず、すごすごと引き返してゆく。いみじくも「忍び返し」とは名付けたものだ。 |
 |
||
| 忍び返しの塀がある旧家は「曲水宴」を醸造していた双葉酒造だ。明治2年(1869)の創業で、玄関を入ると、その時の酒類販売許可証の木札がかけてある。許可番号は七一四九七だ。 当主は「双葉酒造という名前は、戦後株式会社になってからの名称で、それ以前は大坂屋という名前で商売をしていました。家のことを『大伝』と呼ばれます。これは代々の当主が伝次郎とか伝四郎とか伝の字が付いているので、そのように呼ばれました。ちなみに私は伝郎です」といわれる。 曲水宴とは優雅な名前だ。平成4年(1992)に製造を中止したので、幻の銘酒を飲むことはできない。曲水宴という名前にふさわしく、さだめしまろやかな酒にちがいないと思って聞いてみた。 「このあたりはふんだんに伏流水がわき出ていました。硬水でできた酒のようにぴんと腰のある酒ではない。水が柔らかなので、酒も柔らかなものでした」 曲水宴は古代に朝廷で行なわれた年中行事だ。桃の節句の日、朝臣が曲水に臨んで、上流から流される杯が自分の前を過ぎないうちに詩歌を詠じて杯をとりあげ酒を飲み、つぎへ流す。終わって別堂で宴を設けて披講(歌を読み上げること)する。中国から伝わった行事だという。 おそらくは、雅やかな宴にふさわしい酒という意をこめて曲水宴という銘酒ができたのであろう。 「創業したころは、稲置街道を往来する人たちが、家に立ち寄り酒を飲んでいきました。酒と物物交換をした刀なども残っています」 庄内川を渡り、ほっと一息をつく所。小牧、春日井を過ぎて、これから坂をあがり川を越えようとする人が立ちどまる所、それが大坂屋であったのだ。 大坂屋は明治2年(1869)に酒造業を始める前は味鋺の大地主であった。大量の地券が今も保管されているという。徳川家の紋章の入った品物もあるそうだ。 「母親が言っていました。成瀬家が東区の下屋敷を解体した時にいただいたのが、私の家の離れだそうです」 広大な屋敷の北側にある建物が離れだ。 稲置街道は、尾張藩の家老であり、犬山の城主である成瀬家の代々の当主が往還する道だ。味鋺の庄屋とは、犬山との往き帰りに休息をしたりして、特別昵懇の間柄であったろう。 稲置街道を通る人が、休息をした大坂屋、その忍び返しのある塀のつづく屋敷は、街道の往時をしのばせる大切な文化財だ。 (本稿は故沢井鈴一氏記述) (追記) 現在、建物は名古屋市の登録地域建造物資産になっている。水屋敷は江戸末期、主屋は明治期の建築。 |
|||
|
|
|
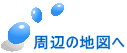  |
|