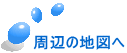|
句碑は、昭和20年(1945)の空襲で、大きく破損してしまった。焼跡から残石をひろい集めて、モルタルで継ぎあわせて句碑に仕立てたものが現在建っている。
碑の上部中央に大きく「芭蕉翁」、その左に句が彫られているが、一行目は数文字見られるが判読できず、二行目は「似(にず)」、三行目は上下が破損し「三日の」部分が残るが「三」は上が破損し「一」になっている。下部に「寛保三癸亥 □月十二日 當五十回忌 於造立之」とあり、判読できない一字は、芭蕉の命日は陰暦の十月十二日なので「十」であろう。
句の一部が欠けたりしているので、三日月塚復原会により昭和24年10月に新しい句碑が横に建立された。
空襲の痕跡は碑だけではなく、鳥居や境内に座す釈迦如来石像などにも残っている。
◇芭蕉堂
また昔は境内に芭蕉堂も建てられ、芭蕉像が安置されていた。『葎の滴』に芭蕉像が盗まれたので新しく作って再設置した話が載っている。安政6年(1859)11月に知人の古屋長太郎から聞いた話として
「了義院の芭蕉堂にある木像は、翁が亡くなってすぐの頃に作られたもので古い像だった。藩士で俳句好きの大熊兔農(とのう)が寄附したものだが、いつの間にか盗まれてしまった。噂では荒井村(現:南区)の俳句好き永井松右衛門が盗んで家に置いているとのことだ。こんなことがあったので大熊は最近有志と相談して新しい木像を作り再びお堂に納めた。」
『東大曽根町誌』には、句碑の背後に芭蕉堂があり、位牌と像が安置されていると書かれており、昭和16年(1941)頃はまだ存在していたが、空襲で失われたようである。
|

元の句碑
(空襲で破砕されたものを再生)

戦後に設置した新しい句碑
|