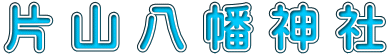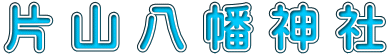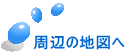境内の様子
|
|
◇末社……6社
本殿右手奥に小社が並んでいる。
愛宕社(日本武尊)、金刀比羅社(大物主命)、青麻社(天之御中主神、天照大御神、月読神)、津島社〔素盞鳴尊、大穴牟遅(おおあなむち)命〕、秋葉社(火之迦具土神)、宗像社〔奥津島比売(おきつしまひめ〕命、市寸島比売(いちきしまひめ)命、多岐都比売(たきつひめ)命)の6社である。
|

|
|
 |
◇谷龍神社
境内北東に鎮座している。
もとは徳川邸(現:徳川園など)に鎮座し、姫子龍神社と呼ばれていた。大正12年(1923)にこの地へ遷座した。
祭神は闇淤加美神(くらおかみのかみ)で、雨をつかさどる竜神である。
|
|
◇御嶽神社遙拝所
この地方で盛んな御嶽教の施設である。遙拝とは離れたところから拝むことなのでここには社殿はなく、御嶽山を拝むための施設である。
|

|
|
◇すべり山
『尾張名陽図会』を見ると、境内の右端に「すべり山」「弘法大師行場」と書かれている。
昔弘法大師が熱田に参籠され、100日の間、5の日ごと龍泉寺へ参詣された。その時、護摩を焚いて修業した場所で、草木が生えないので「すべり山」と呼ばれた。その時閼伽(あか、仏に供える水)を汲んだところが「閼伽塚」で、それが転じて「赤塚」の地名になったという。
なお、「東大曽根町誌」(刊:昭和16年)には「今は全く破壊せられて昔を偲ぶ俤(おもかげ)がない」と書かれている。
|
|
◇瑞龍神輿
平成8年(1996)から始まった神輿巡幸のため造られた。名前の「瑞龍」は、この神社を再興した2代藩主光友の戒名「瑞龍院殿」に依る。
|
 |
|
◇城東耕地整理竣功之碑
明治になり名古屋は城下町から近代的な産業都市へ変身していった。初期の頃は旧市街地のなかに工場などが建設されたが、だんだんと一杯になり周辺部に立地するようになってきた。
当時の城北地域は田園地帯であったが、名古屋の繁栄を見て、自分たちの村も道路などの都市基盤を整備すれば繁華な場所へ変わると考え土地区画整理事業を始めた。当時はまだ都市計画法がなかったので、市街化に向けた事業だが耕地整理法を適用して事業を始めた。最初に設立されたのが城東耕地整理組合で大正元年(1912)の設立で、黒川以南の地域を事業区域にした。
|

|
|
事業が進むにつれ当時盛んだった製糸・織物などの大きな工場が進出し、城北地域は繊維関連産業が集中する地域になった。施工区域の内、五区(六郷村・大曽根町)の事業完了を記念して昭和13年(1938)に建立された碑である。
碑には次のように記されている(旧字は新字に改めた、□は判読不可)
「我名古屋市之周辺田園相接梗称相連所以有田園都市之目也以是民間夙有耕地整理組合之組織焉城東耕地
整理組合亦其一区域広□分十一区六郷村大曽根町則其第五区也而第五区之耕地整理以大正二年一月起工
以昭和二年十一月竣工尓来市之発展顕著而人口日増加大正八年都市計画法制定於是乎竢都市計画路線之
発展□土地利用法以為肆塵地□也道路井然家屋櫛比大改昔日之観矣此地者名古屋市之咽喉而貨物之集散
四氏之出入□多将来之殷賑不可測也大正十一年編入名古屋市称東大曽根町城東耕地整理総工費九十五万
余円内東大曽根町以屢変更設計工費要巨額総工費実十七万七千余円也其間関係諸氏軽私重公忘寝食日夜
□□而後完成焉嗚呼此挙雖由政府保護之厚非官民一致協心□力安能成此大業哉項者東大曽根町組合諸氏
相謀欲建碑以伝後昆来□余□乃叙其梗概云爾 昭和十三年三月中浣 泰山 堀尾茂助撰并書」
概略次の内容である。
この名古屋周辺地域は田園都市のような景観であった。民間で城東耕地整理組合をつくったが、区域が広いので11区に分け、六郷村と大曽根町は第五区であった。この工区は大正2年1月に工事を始め、昭和2年11月に竣工した。それ以来大きく発展して人口が増えていった。大正8年には都市計画法ができ、家が建ち並び昔の面影はない。この地域は名古屋の咽喉部という場所で、貨物や人の出入りが多く、将来の賑わいは予想もできない。大正11年に名古屋市へ編入され東大曽根町になった。城東耕地整理組合の総工事費は95万円余であるが、東大曽根町はしばしば変更設計を行ったので17万7千円余の巨額になった。関係者の寝食を忘れた尽力で事業は完成した。政府の保護があったが、官民が一致し心を合わせたから大事業ができたのである。組合員が碑を建てたいと言うことなので、後の時代の人のために概略を書いた。
昭和13年3月 堀尾茂助
|