
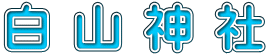
大曽根駅の北東700mに、白山神社が鎮座している。普段は静かな神社だが、広い境内に入ると矢田村の人々が神社に寄せた思いや時代の変遷を感じさせる、さまざまな物が残されている個性的な神社である。
 |
|||
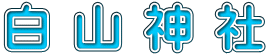 |
|||
大曽根駅の北東700mに、白山神社が鎮座している。普段は静かな神社だが、広い境内に入ると矢田村の人々が神社に寄せた思いや時代の変遷を感じさせる、さまざまな物が残されている個性的な神社である。 |
|||
|
|
|||
| 白山神社の旧社格は村社であるが、創建の時期などは不明である。 江戸時代前期に編纂された『寛文村々覚書』には、「六社大明神 社内六反歩 前々除 瀬古村袮宜吉太夫持分、白山 神明 社内年貢地 当所 漸東寺持分」と書かれている。 『愛知県神社名鑑』によると、元は漸東寺境内に鎮座していたのが現在地へ遷座したとのことである。 |
|||
| 江戸時代以前からある社寺は前々除(非課税地)になるのが普通だが白山神社は年貢地になっている。 江戸時代初期、矢田村には独立した神社としては六社明神(現:六所神社、旭丘高校付近)しかなかった。その後、寛文年間(1661~73)以前に、漸東寺内に祀られていた社が独立した神社になったのであろうか。 現在は矢田川から少し離れた立地だが、明和4年(1767)の矢田川洪水以前は、矢田川がすぐ北を流れていて、堤防際に鎮座する神社であった。 |
 『矢田村絵図』 |
||
| 祭神は菊理比売(くくりひめ)命と天照大御神である。本殿右手に津島社・秋葉社・社宮司社が並び、少し離れた石組みの上に稲荷社と表示のない社が鎮座している。無表示の社は脇に役行者像があるので御嶽神社と考えられる。 |
|||
 津島社・秋葉社・社宮司社 |
 稲荷社・御嶽社? |
||
| ◇手水舎 手水舎は古くはなっているものの手の込んだ造りで、柱が軒桁を支える部分には斗栱(ときょう)が設けられ、天井は格天井になっている。さらに格天井の四隅には白山神社の神紋である三子持亀甲瓜花(みつこもちきっこううりのはな)紋(三重の亀甲の中に瓜の花)が描かれている。これほどの造りの手水舎は珍しい。 |
 |
||
| ◇「少年少女日参団」石柱 手水鉢手前に建つポールには「支那事変記念」「日参少年少女団」「皇紀二千六百年」の文字を刻んだ石柱が添えられている。昭和12年(1937)に勃発した日中戦争を記念して15年(1940)に建てたものだ。 「日参少年少女団」は戦意高揚を狙って組織されたもので、子どもたちが集団で神社に毎日参拝し戦勝や兵士の武運長久を祈願した。 『愛知・名古屋の戦争遺跡』(著:伊藤厚史氏)には「全名古屋市日参少年少女総連合団は、名誉総裁に前上海方面軍最高指揮官陸軍大将松井石根、総裁に陸軍中将大塚堅之助中将をすえ、七〇〇余団体と七万有余名の団員から構成されていました。昭和一三年一一月四日の『新愛知』には一五〇〇団体、一〇万余と報道されています。」と書かれている。 この神社にも、戦争中は毎日子どもたちが隊伍を組んで祈願に訪れていたのである。 |
 右:「支那事変記念」 左:「日参少年少女団」  「皇紀二千六百年」 |
||
| ◇神楽殿 拝殿右手手前に神楽殿が建つ。 正面の軒下ににこやかな笑みを浮かべたお面が三つ掲げられているのは珍しい。年月を経て木目が浮き出し、立体感が増している。 |
 |
||
| ◇拝殿 社名を書いた額に「陸軍中将正四位勲二等功三級山田虎夫謹書」とある。 昭和3年(1928)刊行の『人事興信録』によると次の経歴である。 山田は明治2年(1869)に愛知県士族の子として生まれ、24年(1891)に陸軍士官学校を卒業、各地の連隊長を務めて大正5年(1891)にはシベリア出兵に従軍し、十年(1921)に陸軍中将に昇任し第6師団長(熊本)となり、12年(1923)に予備役編入になった。住所は「名古屋 中 御器所町」と書かれており、予備役編入後は名古屋に住んでいた。 拝殿の軒下には立派な干支の彫刻が掲げられている。3枚足りないが、拝殿の中を見ると鳥・寅・犬が掲げられている。 |
  |
||
| ◇切り株の将棋盤 境内に切り株に線を掘って造られた将棋盤と、その横に丸太で造った椅子が置かれている。 神社は戦争勝利祈願に子どもたちが日参する場ではなく、境内でのどかに将棋を指す、そんな時代が続いてほしいと思う。 |
 |
||
|
|
|
  |
|