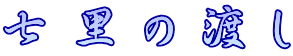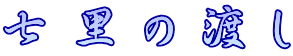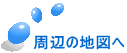七里の渡し
|
|
◇渡船の数
渡海のための船は、宝暦元年(1751)に幕府の道中奉行が熱田に来たときには100隻と答えている。
また江戸時代後期に編集された『東海道宿村大概帳』には、「現在75隻だが、大きな通行があるときは藩に申し出て桑名や近隣の村から借りる」と書かれている。併せて「小渡船42隻がある。これは熱田の海岸が浅いので、干潮時には渡し船は水深の深い沖に停泊し、小渡船で客や荷物を渡し船まで運ぶ」との記載がある。渡し船は20~100石の船が使われた。
◇渡し賃
渡し賃は天和2年(1682)時点では、人は30文、荷物は1駄(馬1頭分の荷物。135㎏)70文であった。
だんだん値上がりし、宝永4年(1707)には、人は45文、一駄は109文になっている。天保年間(1830~44)には人は63文、一駄は151文になった。
渡し場の様子につて『尾張名所図会』は「あしたには七里の渡一番船をあらそひ、船場には商賈の荷物つどひて山のごとく」と、その賑わいと喧噪を記録している。
|

『名古屋市史』
|
|
◇海難事故
海難事故も起きている。
琉球使節一行は江戸参府を終えて帰国するため、寛文11年(1671)11月27日、51隻の船に分乗して熱田から桑名へと出発した。
4~5里(16~20㎞)ほど進んだ頃、にわかに天候が変わって強風が吹き、正使と副使が乗る2隻は多屋村(現:常滑市)と大野村(同上)へ漂着した。下級使節員が乗る5隻は現在の常滑市と鈴鹿市に漂着したが、幸い使節員・護衛の薩摩藩士とも犠牲者は出なかった。
このことがあったので、正徳4年(1714)からの使節は、美濃街道経由にルートを変えている。
|

琉球使節 漂着
『小治田之真清水』
|
|
また、天保6年(1835)2月11日、疾風が吹き雨が降る天候のなか、桑名から熱田へ来る船が1艘沈み、4人が亡くなった記録も残っている。
舟が小さく天気予報もない時代なので、七里の渡しは危険も伴う旅であった。
|
|
◇新東海道完成 役割を終える
明治5年(1872)に新東海道(前ヶ須街道)が完成すると、七里の渡しは東海道の本筋ではなくなり、長年担ってきた役割を終えている。
|

『尾張国全図』 明治12年 |